【事例紹介】モック屋発・DF事業部の挑戦、誰も触らなかった魔法の箱を武器に|株式会社エムトピア
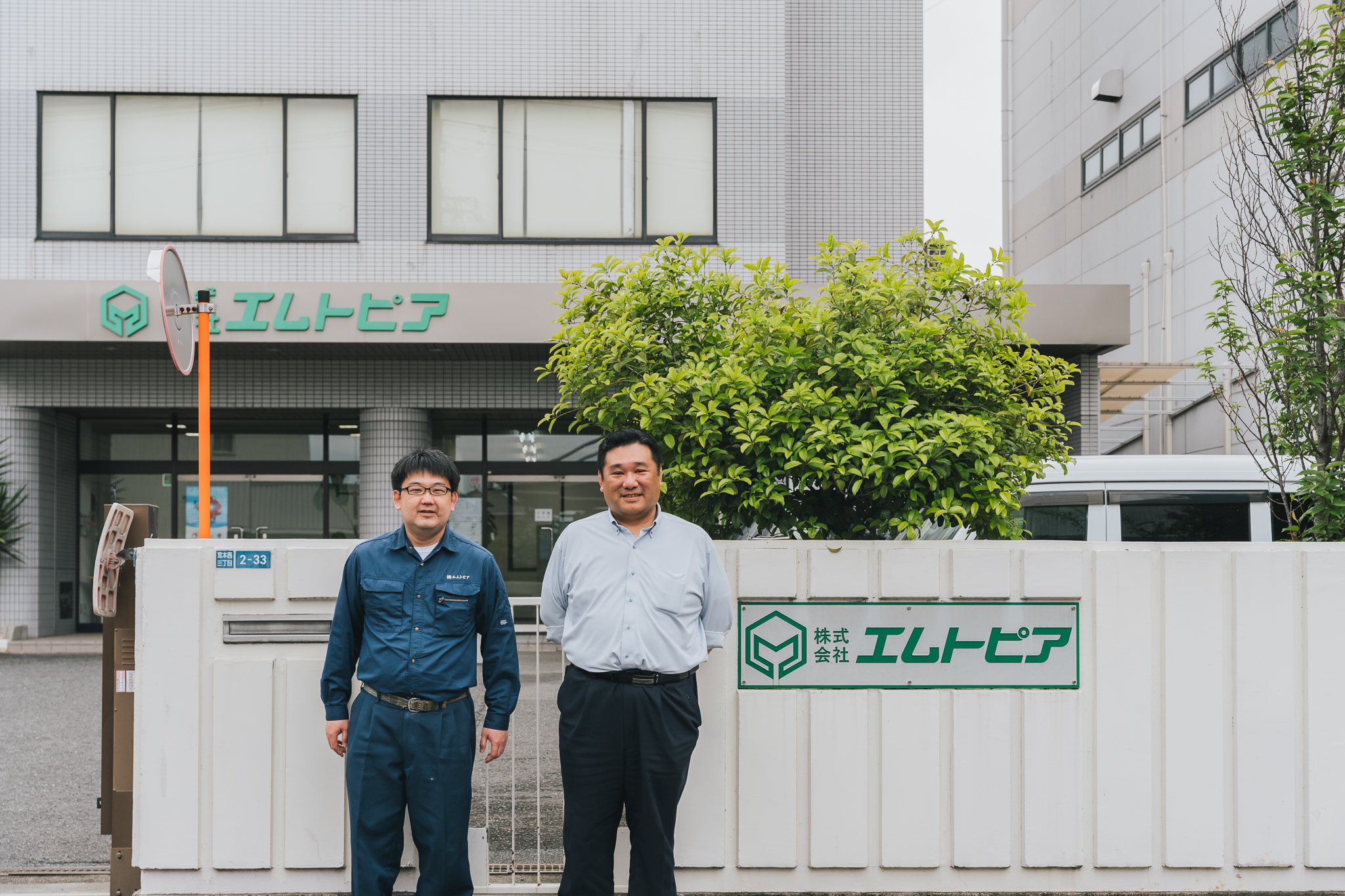
Yokoito Additive Manufacturing(YAM)で導入支援をした光造形方式3Dプリンター「Form 4」、SLS方式3Dプリンター「Fuse 1+」を活用した事例として、株式会社エムトピア(以下、エムトピア) DF(Digital Fabrication)事業部の取り組みを紹介します。
大阪府東大阪市に本社を構えるエムトピアは、家電や自動車内装のデザインモック製作で知られる老舗試作メーカーです。昭和の木型彫刻に始まり、光造形、インクジェット、FDMと“最新”を求めて数々の3Dプリンターを導入してきましたが、切削と塗装が主軸の現場では「削った方が速い」と敬遠され、機械が倉庫で眠ることもしばしばありました。
今回のインタビューでは DF 事業部の久保さんと常務取締役の林さんにお話をうかがいました。
久保さんが笑い交じりに振り返る「せっかく買ったのに半年間だれも触らへんかった」という過去から、Form 4で掴んだ手応え、そしてFuse 1+で狙うビジネスまで、“試作屋”がデジタルとどう折り合いを付け、現場を動かしたかを追います。
取材ご協力:
株式会社エムトピア 常務取締役 兼務 営業本部長
林 真広 様
株式会社エムトピア DF事業部 ーDigital Fabrication Divisionー 3Dプリンターオペレーター
久保 信千加 様
モックアップ一筋55年。見た目が命の試作文化
――御社について教えてください。
林 創業は昭和40年代で、白物家電の試作モック専門からスタートしました。前回の大阪万博を機に仕事が一気に増え、今では名古屋・横浜・浜松、海外はベトナムにも製造拠点があります。
久保 社長は今も「うちはモック屋や」と言い切ります。昭和の木型手彫りから始まり、マシニングや塗装設備をそろえてきましたが、“見た目を人の手で担保する”という文化は変わりません。デザイナーさんの意匠を形にする。それがずっと会社の基盤です。
――家電以外の分野にも広がっていますか。
林 近年は自動車の内装部品やテーマパーク什器、アート展示の造形なども増えています。国内で白物家電の試作が減る一方で、新しい領域に軸足を移すことで売り上げを維持している状況ですね。

魔法の箱の現実とDF事業部発足
――最初に3Dプリンターを導入したのはいつでしたか。
久保 リーマンショック前です。最初に光造形(SLA)を入れて、そのあと大型インクジェットとFDM。でも半年、誰も電源を入れなかった。
林 FDM は横から弾くと折れるし、積層痕は目立つ。材料費だけ膨らんで「削った方が早い」と現場が言い出しました。
久保 当時は“何でも一発で作れる魔法の箱”と盛り上がったけど、実際は治具と後処理が山ほど要る。切削の方が手順もコストも読めたんです。
――それでもDF事業部を立ち上げた経緯を教えてください。
久保 社長が「デジタルを推進せえ」と号令をかけたんです。専任5人を抜擢し、設備も場所も“まず与える”方式。大型インクジェットでバイクのサイドカーを一体造形したり、仏像を 3D スキャンして博物館へレプリカを納めたりと、実験的な案件を次々こなしました。1件 1,000 万円規模のモックもあります。
林 ただ、展示会が終われば倉庫行きというケースが多く、継続案件にはなりにくかった。品質は抜群でも、お客様が毎回その金額を出せるわけではありませんから、社内でも「結局何に使うんや」という冷めた声は残りました。

Form 3シリーズ導入で「置物」が「道具」になった瞬間

――3Dプリンターに対する社内の評価を変えたきっかけは何だったのでしょうか。
久保 Formlabsの Form 3を触ったときです。ラバーライク材料の反発が想像よりはるかに良くて、デザイナーが一目で「このまま組める」と食いつきました。
――コスト面ではどう受け止められましたか。
久保 本体はおよそ50万円というレンジだったので、社長も「その価格なら試してみろ」と即決でした。そこで“ゴム系専用機”と割り切り、硬度の違う3種類を5パターンまとめて造形する運用を始めたんです。
――エンドユーザーの反応はいかがでしたか。
久保 「試作の初期段階から複数パターンを同時に比較できるのが助かる」と評価いただきました。ここで初めて、社内でも プリンタが“置き物”ではなく“使う道具”だと認識が変わった実感があります。
林 従来は見た目を人の手で担保する文化が強かったのですが、Form 3シリーズのラバーライクは仕上げなしでも現場基準を満たせる。小さな機械が、大きな突破口になりました。


Fuse 1+で探る使える3Dプリントへの道
――Form 3で手応えをつかんだあと、Fuse 1+の導入にも踏み切られたそうですね。
林 はい。メーカーさん側から 3D プリンタ指定の試作案件が増え、「光造形だけでは足りない」と感じる場面が目立ってきました。さらに、 Fuse 1+ が「うちの作業場に置けるサイズと価格」だったのが決め手です。従来機のようにクレーン搬入も要らず、材料管理から後処理まで1カ所で回せる。これならいける、と思いましたね。

――導入が決まり、社内にはどんな変化が起こりましたか。
林 これまで以上に柔軟な数量への対応や、より実運用に近い条件での検証が可能になりました。ただし、量産保証の社内ルールはまだ手薄です。検査治具や再現性チェックを整備しないと、お客様に最終部品として出荷できません。
――課題がはっきりしてきたわけですね。
久保 ええ。昔は 「プリンタを入れても何をしたらいいか分からない」 状態でしたが、今は 「検査フローと後処理ラインをどう作るか」 と具体的です。外からは迷走に見えるかもしれませんが、試作屋が小ロット生産まで踏み出すなら仕込みの時間は不可欠です。ようやく本当のスタートラインに立てた気がします。
お客様の声を背に次の一歩へ
――お客様からの反応はどうでしょうか。
久保 以前は「とにかく3Dで何か作って」でした。それが今では 「この機種の、この材料で」 と指名が来ます。過去に光造形やインクジェットで散々試したおかげで、提案の厚みが増した証拠だと思います。
林 設備の選択肢はそろいました。次は“人と仕組み”。切削と塗装は当社の強みですから、Fuse 1+で造形したナイロンやエラストマーを社内で仕上げまで完結できれば、コストも納期も一段下げられるはずです。
久保 “置物”だったプリンタを“道具”に変えられるかどうかは、ここからの足固め次第。10 年先を見据えて、一つずつ課題を潰していきます。

――Fuse 1+ が稼働し始めたいま、まず取り組むことは?
久保 検査フローと後処理ラインを“標準業務”に落とし込むことです。粉末造形を小ロットで回すなら、再現性チェックや検査治具が社内にないと話になりません。
林 そこが整えば、より実用性を意識した仕上げや検証にも対応できるようになるはずです。まずは Fuse 1+を24時間運用できる環境をつくり、“市場投入前の最終検討段階にも対応し得る試作品”を正式メニュー化できる、それがDF事業部のマイルストーンですね。
久保 設備は揃いました。次は人と仕組みです。そこを整えた先に、 塗装・切削と粉末造形の組み合わせによる当社ならではのハイブリッド製造が本当に花開くと思います。
――貴重なお話をありがとうございました!

魔法の箱を道具に変えるまで
光造形、インクジェット、FDMと3Dプリンターの導入で何度も苦い思いをしてきたエムトピアDF事業部。導入当初は材料費が月500万円に膨れ、FDMパーツはもろく、現場からは「削った方が早い」と突き返されたこともあったそうです。それでも歩みを止めず、光造形機で小さな成功をつかみ、今はFuse 1+を核に粉末造形へ踏み出しています。
久保さんは長年の歩みを経てこう言葉を残しました。
「プリンターを入れただけでは起爆剤になりません。でもこの機種の、この材料と指名で相談が来るようになった。次は検査と後処理を整える番です。そこさえ固まれば、うちの試作はまだ伸びます。」
昭和の木型から始まった“見た目を担保する文化”は、デジタルの選択肢を増やしさらなる飛躍を予感させます。エムトピアが培ってきた審美性と機能をどのように活かしていくのか、今後も非常に楽しみです。

エムトピアホームページ| https://emtopia.net/
<本件に関するお問い合わせ>
平日 10:30-17:00
Mail: pr@yokoitokyoto.com




